-
最近の投稿
アーカイブ
カテゴリー
投稿日カレンダー
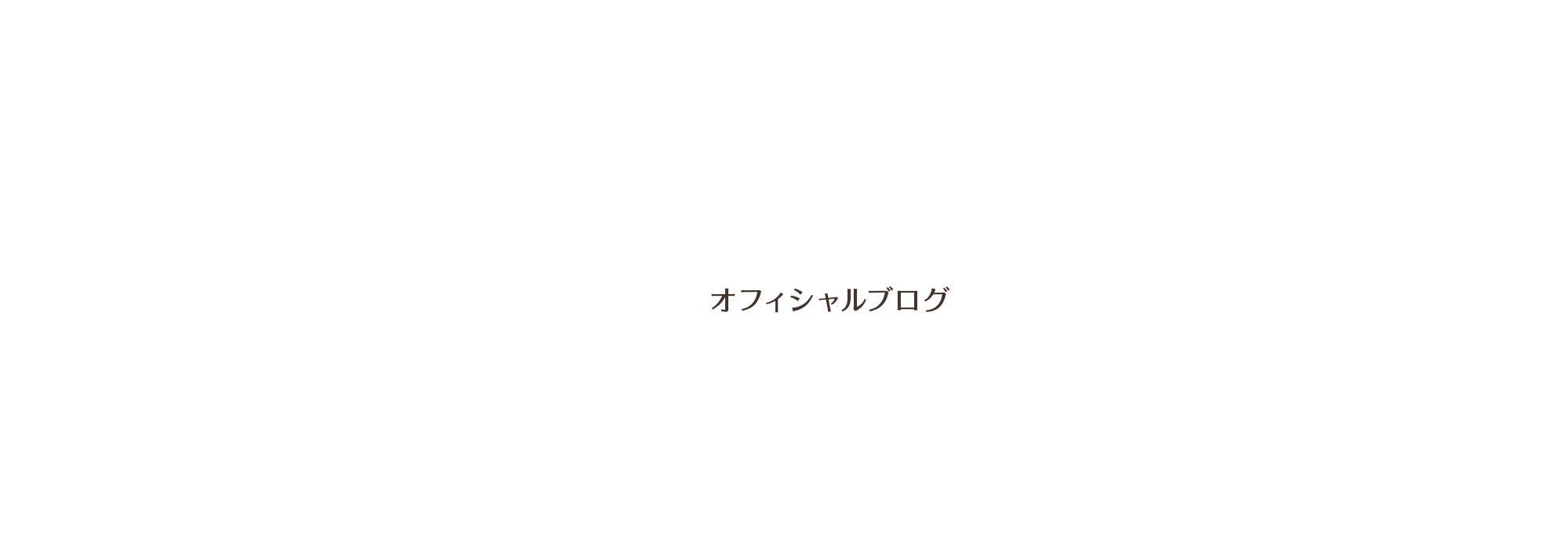
皆さんこんにちは!
m´jun、更新担当の中西です。
さて今回は
介護保険について
ということで、ここでは、日本における社会保障制度のひとつである「介護保険制度」について、その仕組みと背景、課題を深掘りしてご紹介します!
介護保険とは、高齢者が介護が必要になっても、できるだけ自立して暮らせるように支援する仕組み。私たちの暮らしと将来に直結する、大切な制度なのです。
介護保険制度は、高齢者や障がいのある人が、安心して介護サービスを受けられるようにするための社会保険制度です。
制度の基本理念は以下の3つ
自立支援:できることは自分で。できない部分を支援する。
利用者本位:本人がサービスを「選ぶ」立場に。
社会全体で支える:保険料と税金で支える「共助」の仕組み。
| 年 | 出来事 |
|---|---|
| 2000年 | 介護保険制度スタート(65歳以上の保険加入が義務化) |
| 2006年 | 予防重視の「地域包括ケア」導入開始 |
| 2012年〜 | 地域密着型サービス拡充、医療と介護の連携強化 |
| 2021年〜 | 科学的介護・ICT導入によるサービスの見える化促進 |
📌 高齢化の進行を受け、「家族介護の限界」を背景に誕生した制度です。
介護保険の対象者は次の2種類に分かれます
| 区分 | 対象 | 内容 |
|---|---|---|
| 第1号被保険者 | 65歳以上 | 原則すべての人が加入義務あり |
| 第2号被保険者 | 40~64歳の医療保険加入者 | 老化に伴う特定疾病がある人が対象 |
介護保険サービスを利用するには、要介護認定を受ける必要があります。
市区町村に申請
調査員による訪問(要介護度の判断)
主治医意見書の提出
介護認定審査会による判定
要支援1~2、要介護1~5の区分が決定
この判定に基づいて、受けられるサービスの内容・量が決まります。
介護保険には、在宅・施設を含めて多種多様なサービスがあります。
訪問介護(ホームヘルプ)
訪問入浴・訪問看護
通所介護(デイサービス)
短期入所(ショートステイ)
特別養護老人ホーム(特養)
介護老人保健施設(老健)
介護医療院(医療対応型)
小規模多機能型居宅介護
認知症対応型グループホーム
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
📌 利用者本人とケアマネジャーが相談しながら、必要なサービスを選んで組み合わせます。
原則として、介護保険サービスの利用者は費用の1~3割を自己負担します(所得に応じて異なる)。
| 所得区分 | 自己負担割合 |
|---|---|
| 一般的な所得層 | 1割負担 |
| 一定以上の所得 | 2割または3割負担 |
また、サービスには「支給限度額(月額)」があり、それを超える分は全額自己負担となります。
介護職員の確保が追いつかない
サービスの質を保ちながら、量も増やす必要がある
高齢者人口の急増により、保険料・税負担が増加
サービスの範囲や給付の見直しが検討されている
都市部と地方で、受けられるサービスの質や種類に差がある
特に過疎地では訪問介護の担い手不足が深刻
「どこに相談すればいいのかわからない」
制度が複雑で高齢者や家族が混乱するケースも
介護データを活用した「エビデンスに基づく介護」
センサー・AI・記録アプリなどを活用した業務効率化
医療・介護・生活支援・住まいを一体で提供
「最期まで住み慣れた地域で暮らす」ことを実現する取り組み
給付範囲や自己負担の見直し
民間保険や自助・共助の組み合わせの検討
介護保険制度は、今の高齢者のための仕組みであると同時に、いずれ自分自身も関わる「未来の安心」でもあります。
👥「介護保険に頼らずに済む」が理想かもしれない。
でも「頼れる制度がある」ことは、確かな安心につながる。
誰もが老いと向き合う時代だからこそ、介護保険制度について正しく理解し、支え合いの心で活用していくことが大切です。
私たちm´junは、この沖縄にお住まいの方々を対象に、
「居宅介護」「デイサービス」「自費サービス」を展開しています。
いつでもお気軽にご連絡下さい。
![]()